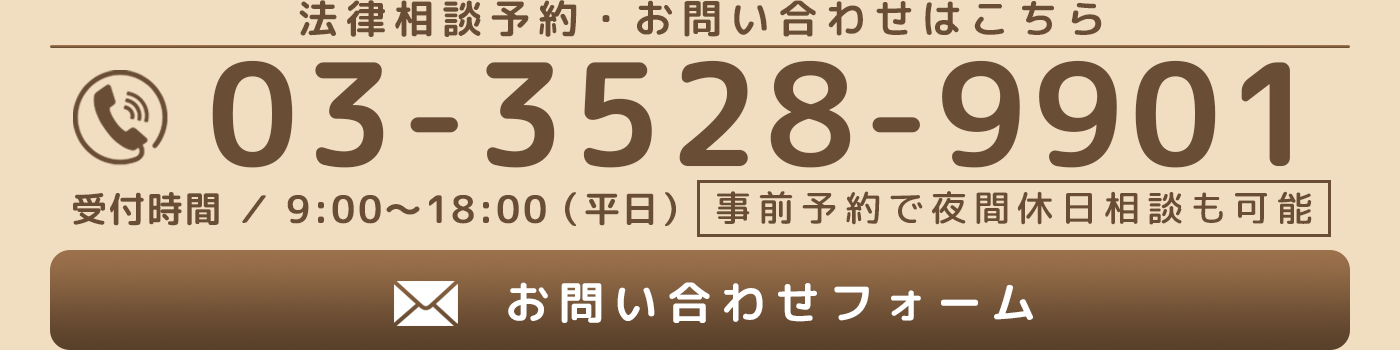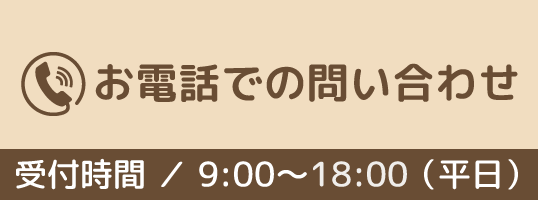相続は多くの方が経験することであり、日頃親族間で仲良くしていても、ちょっとした行き違いなどで相続トラブルに発展することもあります。
そこで以下では、遺産相続の相談事例やトラブル事例をご紹介し、それに対する予防方法や対処法をご案内します。
遺言書に関するQ&A
遺言書が発見された場合の対応
家庭裁判所で検認してもらう
自筆の遺言書(自筆証書遺言)は、法律上、見つかった時点で、すみやかに家庭裁判所に「検認の申立て」をしなければなりません。家庭裁判所では、相続人の立会いのもと、遺言書が開封され、検認の手続がなされます。
検認手続きでは、裁判官が、遺言書に封がされているかを確認し、封がされている場合には開封して、記載内容を読み上げます。その後、立会いの相続人にその筆跡と印影を見せて確認してもらい、被相続人の筆跡、印鑑であるかを確認します。
その確認結果等については、裁判所で調書を作成して記録化しますが、検認は、あくまでも遺言書の形式的な要件を満たしているかを確認するにすぎず、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
なお、発見された遺言書を検認前に勝手に開封してしまうと、他の相続人から偽造などを疑われるおそれがありますので、開封してはいけません。また、開封した場合、5万円以下の過料が課せられる場合がありますので、開封せずに、まずは家庭裁判所に持参して、検認してもらわないといけません。
遺言書の書き方・形式・適切な保管場所
公証役場で公正証書遺言を作成するのがおすすめ
一般的な遺言書(形式・方法)には以下の3つの種類があります。
① 自筆証書遺言
遺言者が自分で作成する遺言で、本文の全文・日付・氏名を自筆(パソコン、代筆などは不可)で書いて捺印します。自宅ですぐに作成できて手軽である反面、法律上の形式に不備があったり、内容が不明確である場合など、遺言者の死後に遺言が無効と判断されるリスクもあります。
また、遺言者の死後に、家庭裁判所の検認が必要であり、手続きが面倒であるため、当事務所ではあまりおすすめしていません。
② 公正証書遺言
遺言者が公証役場に行き、遺言内容を公証人に告げて、公証人が公正証書遺言を作成します。その際、最低2人の証人の立会いが必要となります(証人が用意できない場合は、有料ですが公証役場で用意してもらうこともできます)。
作成された公正証書遺言は、公証役場に原本が保管され、全国どこでもオンライン検索が可能ですので、相続人が遺言書の存在を認識しやすいメリットがあります。
また、法律の専門家である公証人が作成しますので、遺言の形式などに誤りがなく、後日紛争化することを防止できます。
さらに、家庭裁判所における検認手続も不要であるため、遺言書を書くのであれば、当事務所でおすすめしている方法です。
③ 秘密証書遺言
公正証書遺言と同様、公証役場で作成しますが、遺言書を密封して、公証人も内容を確認できない点で異なります。公証人が確認していないため、遺言書の内容が不明確な場合など、死亡後に無効となるリスクもあります。
遺言書の保管場所について、自宅で保管する方法もありますが、紛失やどこにしまったか忘れてしまったり、第三者が盗む、破棄する、改ざんするなどのリスクがあります。そのため、公証役場に原本が保管される公正証書遺言であれば、紛失・改ざん等のリスクはありませんので、おすすめです。
また、自筆証書遺言の場合、法務局が遺言書を保管してくれる「遺言書保管制度」というものがあります。この制度を利用すれば、公正証書遺言と同様、紛失・改ざん等のリスクはありません。
また、保管を依頼する際に、法務局が遺言書の形式面をチェックしてくれますので、形式が不備で無効となることがないうえ、死亡後に家庭裁判所での検認手続きが不要です。さらに、相続人は、全国どこの法務局でもデータで保管されている遺言書を閲覧などできますので、相続人にとってもメリットがあります。手数料も遺言書1通につき3900円と安価ですので、こちらもおすすめです。
詳しくは、下記の法務省のホームページをご確認ください。
自宅以外の遺言書の保管場所
公証役場または法務局
自宅以外で遺言書が保管されていると考えられるのは、公的な機関でいえば、公証役場(公正証書遺言を作成)、または法務局(自筆証書遺言を作成して遺言書保管制度を利用)が考えられます。
いずれの機関も、相続人であれば全国どこでも照会できますので、遺産分割協議を行う前に確認するとよいでしょう。
認知症の方が書いた遺言書の有効性
直ちに無効にはならない
遺言書の有効性について、認知症の人が書いた遺言書だからといって、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。その遺言書が書かれたときに、遺言者が「遺言能力」、つまり遺言内容を具体的に決定し、その結果生じる効果(誰が、何を、どれだけ相続するのか等)を理解するのに必要な判断能力があったかで判断されます。具体的には、認知症の人が書いた遺言の有効性は、主に次の点から総合的に判断されます。
- 遺言時における遺言者の心身の状況(認知症の程度、遺言者の行動など)
- 遺言内容の複雑性(単純な内容か、複雑な内容か)
- 遺言内容の不合理性、不自然性(遺言者と相続人等との関係、遺言に至る経緯等)
すべての相続人が遺言書は無効であると認めた場合は、改めて相続人全員で遺産分割協議をして、遺言書と異なる内容の遺産分割をすることができます。
しかし、遺言書の有効性を争う相続人がいる場合には、家庭裁判所に遺言無効確認調停を申し立てる必要があります。遺言を無効とすることに相続人全員で合意した場合は調停が成立します。
一方、一人でも無効と認めない相続人がいる場合は、調停不成立となり、調停手続きは終了します。その場合は、地方裁判所に対して遺言無効確認訴訟を提起して、遺言書の有効性を裁判所に確認してもらうこととなります。
1人の相続人に全て相続させることの問題点
遺留分への配慮が必要
遺言書は、遺言者の最後の意思表示であり、自由に作成することができます。長男に「全ての財産を相続させる」という遺言内容も当然に有効ですので、法律的には問題はありません。
ただし、法定相続人が長男、次男の2人である場合、次男には法律上、遺留分が保障されており、このケースでは、次男には遺産額の1/4の遺留分があるため、これを長男に請求することができ、長男は基本的にはこれを支払わなければなりません。
長男が納得して支払えば問題はないのですが、感情的なもつれで紛争化することも少なくありません。
ですので、例えば、次男には遺留分1/4に相当する財産を相続させるなど、次男にも配慮することで、遺言者が死亡した後のトラブルを回避することができます。
なお、遺言者の生前に、次男の了解が得られるのであれば、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄してもらうことも可能ですが、次男が納得していることが前提となるうえ、裁判所での手続きも相応の手間がかかりますので、あまりおすすめできません。
相続のやり直しの可否
相続人全員の合意があれば相続のやり直し(遺産分割協議)が可能
遺言は、被相続人の最後の意思表示ですので、基本的には相続人はこれに拘束されます。
しかし、相続人全員が遺言の内容に反対する場合、相続人間で協議を行い、相続人全員が納得のいく形で遺産分割を行うことができます(遺言執行者がいる場合はその了承を得る必要があります)。
但し、遺言書で遺産分割が禁止されていた場合は、相続人全員が合意しても遺言書と異なる遺産分割協議はできませんので、注意が必要です。
遺言執行者は必須か
遺言執行者は必須ではない
遺言執行者は、特別な場合(遺言書で相続人を廃除している場合等)でない限り、必ず選任しないといけないというわけではありません。その場合、相続人全員で協力して、金融機関で手続きを行うなどにより、遺言書に従って遺産を分ければ問題ありません。
相続人全員で協力することが難しい場合や、手続きが複雑で不安な場合などは、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。
不安な方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
遺産分割に関するQ&A
遺産分割協議に出席しない人がいる場合
弁護士に間に入ってもらうことがおすすめ
遺産分割協議は必ず全員で行い、その協議結果を遺産分割協議書にしなければなりません。そうしないと、銀行で預金が引き出せない、不動産登記の名義変更ができないなど、いつまでも遺産が相続できない状態となり、場合によっては相続税の申告期限(被相続人の死亡日の翌日から10ヵ月以内)に間に合わない、その間に相続人の誰かが亡くなり、その人を子や孫が相続して(二次相続といいます)、相続人の数が増えて複雑になるなどの問題が生じかねません。
従って、できるだけ早期に遺産分割協議書を作成することが大切です。
このような場合、協議に出席しない事情などにもよりますが、その人が他の相続人と折り合いが悪いとか、会いたくないなどであれば、弁護士に依頼して間に入ってもらい、協議を進めるという方法をおすすめします。
また、相続人間で不仲である、または意見の食い違いが大きいなどの場合は、相続人間で協議を継続しても解決につながらないことも想定されます。そのような場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、中立的な調停員を介して遺産分割協議を進める方法もあります。
いずれにしても、相続人間で協議が進まない場合は、相続案件の経験豊富な当事務所の弁護士にご相談ください。
連絡がつかない、または知らない相続人がいる場合
弁護士に調査してもらうのがおすすめ
遺産分割には、相続人全員が参加する必要がありますが、相続人のなかには、疎遠になって久しく連絡先が分からない人や、異母兄弟で会ったことのない人がいる場合があります。
このような場合、弁護士は、職務上戸籍や住民票を取得することができ、相続人の住所を把握することができます。また、会ったこともない異母兄弟と遺産分割協議をするのは困難な場合もあるでしょうから、そのような場合も弁護士を間に入れて、円満に協議を進めることをおすすめします。
相続財産がどれだけあるか分からない場合
弁護士に調査してもらうのがおすすめ
相続財産は、被相続人が亡くなった時点での全ての財産及び債務です。
しかし、被相続人から財産や債務の内容を聞いていない場合、相続人が相続財産などを把握するのは困難であり、抜け漏れが生じる可能性があります。
当事務所の弁護士は、相続案件を多数取り扱っておりますので、預貯金、不動産などの調査や、被相続人の有する資料から債務などを確認することが可能です。お困りの場合は、お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。
被相続人の事業の手伝いや介護をした場合、遺産を多くもらえるか
寄与分を主張して、遺産を多くもらうべき
被相続人の生前に、その財産の維持・増加に貢献した相続人には、寄与分というものが認められ、遺産分割で特別な考慮がされます。その理由は、法定相続分で遺産分割をした場合、相続人間で不公平が生じる場合があるため、その調整を行う必要があるからです。
具体的には、被相続人の事業を手伝ってきた、または被相続人の事業に資金援助をしたような場合は、一般的に寄与分が認められますので、寄与分を主張すべきでしょう。
一方、被相続人の介護については、被相続人の配偶者や直系血族などは被相続人を扶養する義務を負っているため、親族間の扶養義務に基づく一般的な介護程度であれば、通常寄与分は認められませんが、介護により扶養義務の範囲を超える大きな貢献をし、それによって被相続人の財産が維持・増加したと認められる場合であれば寄与分が認められることがあります。
ただし、このような場合であっても、どのような介護をしたかを示す客観的な証拠などを準備しておくとよいでしょう。
遺産分割後に遺言書が見つかった場合
原則遺言が優先。但し、相続人全員が合意すれば遺産分割協議書が優先
遺産分割協議後であっても、遺言書が見つかった場合は、原則遺言の内容が優先されます。その理由は、遺言が遺言者の最終意思を表示したであるため、法的に尊重されるべきだからです。
ただ、すでに作成された遺産分割協議書が直ちに無効になるわけではありません。相続人全員がその遺産分割協議書の内容に合意している場合は、その遺産分割の内容を遺言に優先させることができます。
ただし、相続人全員が、遺言の存在と内容を知ったうえで合意しなければなりません。
なお、遺言によって認知がされている場合や、相続人以外の第三者に遺贈するといった内容が遺言に含まれる場合は、本来遺産分割協議に参加すべき人が参加していないことになり、相続人全員が参加していないことになりますので、それらの人も加えて遺産分割をやり直す必要があります。このような複雑なケースでは、弁護士に相談することをおすすめします。
遺留分に関するQ&A
遺言書で自分に相続分がない場合(遺留分を請求したい場合)
遺留分を請求する
法律上、被相続人(亡くなった方)の近しい関係にある法定相続人に最低限保障された遺産の取得分があり、これを遺留分といいます。遺留分が法律上認められた理由は、被相続人の近しい関係にある法定相続人、例えば、子などであれば、被相続人が財産(遺産)を増やしたり、維持したりすることに貢献しているはずですから、子などの近親者が一切遺産を相続できないとすることは不公平であるためです
このケースでは、弟の遺留分として1/4が法律上認められますので、兄に対して、「自分の遺留分1/4を侵害しているから支払え」と請求することができます。
ただし、遺留分を請求できる期間は、「相続が開始して遺留分の侵害を知ったときから1年以内」ですので、すみやかに請求することが必要です。遺留分の金額が分からない、請求の方法が分からないなど、ご不明な点があれば、当事務所の弁護士にご相談ください。
遺言書で自分に相続分がない場合(遺留分を請求された場合)
すぐには支払わず、まずは時効、請求内容などを精査する
遺産を取得できなかった弟には1/4の遺留分がありますので、最終的には支払わなければならない可能性があります。
ただし、すぐに請求内容通りに支払うのではなく、弟が相続を知ったときから1年経過していないか(時効消滅の可能性)、請求額(遺留分の算定)は適正か、弟は生前に父から贈与を受けていないかなどを確認しましょう。場合によっては、支払う必要がない、又は請求額より少ない金額を支払えば足りることもあります。
その他、遺留分を請求された場合にいくつかチェックしたほうがよい点もありますので、遺留分を請求された場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
不動産の評価に争いがある場合
唯一絶対の評価方法・ルールはないが、遺留分を請求できる場合がある
遺留分を計算するにあたり、不動産をどのような基準で評価するのかが問題となります。不動産の評価方法には、主に次の4つがありますが、唯一絶対の評価方法・ルールはありません。
- 公示価格(公共事業用地の取得のための計算の基準)
- 相続税評価額(相続税納付用の価格)
- 固定資産税評価額(固定資産税納付用の価格)
- 実勢価格(いわゆる時価)
上記①~④のうち、一般的に最も高いとされるのが④実勢価格です。また、遺留分は遺産がどのくらいの価値であるかにより決定されるものです。
従って、遺留分を請求する弟としては、実際に取引された場合の価格であり、最も高くなりやすい④実勢価格で計算し、遺留分を侵害されていると思われる場合は、兄に遺留分を請求するとよいでしょう。
一部の相続人にだけ生前贈与が行われた場合
生前贈与を含めた遺産額を計算し、遺留分が侵害されていれば請求できる
一部の相続人だけが生前贈与を受けた場合、それ以上の相続人は不公平に感じます。そのため、法律上、相続人に対する生前贈与のうち、相続開始前10年間に行われたものは、遺産に加算し、その額が遺留分計算の基礎となります。
例えば、質問のケースで、相続財産である預金が2,000万円で、相続人である兄・弟で1,000万円ずつ取得し、兄だけが相続開始の直前に6,000万円の生前贈与を受けていたとします。
この場合、<相続財産2,000万円+生前贈与6,000万円=8,000万円>が、遺留分計算の基礎となります。
弟の遺留分は、<8,000万円×遺留分割合1/2×法定相続分1/2=2,000万円>です。
とすると、弟の遺留分は2,000万円であるのに、1,000万円しか遺産を相続していませんので、兄が弟の遺留分1,000万円分を侵害しているため、弟は兄に対して1遺留分1,000万円を請求できます。
まとめ:遺産相続トラブルに巻き込まれたらすぐご相談ください
遺産相続トラブルを未然に防ぐ方法として、相続人間で紛争が生じないよう、各相続人に配慮して遺言書を作成する、生前に家族間で十分に話し合って、お互いが納得できるような相続を考えることなどがあげられます。
しかし、生前に十分な準備をしておくことが難しいことも多いのが現実であり、被相続人の死亡後に、それまで争いごとのなかった親族間に相続トラブルが発生することも少なくありません。
もし、遺産相続トラブルに巻き込まれたときは、ささいなことでも結構ですので、相続案件を得意とする当事務所の弁護士にお早めにご相談ください。